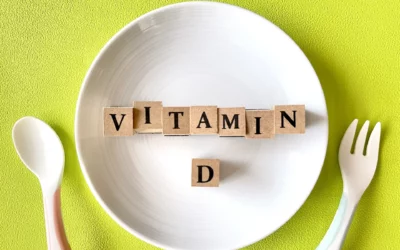日本の国民病とまで言われる花粉症についてお話します。...
ビタミンD
【子どもにも】日本人に急増中!花粉症のインナーケア対策は?【2025最新版】
2025年01月21日 | ブログ
20年間で2倍以上! 花粉症急増の理由...
ビタミンDはなぜ必要? 冬こそ積極的に摂りたいその効果とは
2024年12月16日 | ブログ
今注目されている、ビタミンD不足...
【Web掲載】ELLE デジタルでアクティブサプリが紹介されました
2024年08月20日 | メディア掲載
ELLE Digital(2024/7/8) 「ビタミンDサプリメントのおすすめ人気17選! 選び方・正しい飲み方も専門医師が徹底解説」のなかでアクティブサプリ ビタミンA+Dが紹介されました。 ...
若々しさの秘訣!シワ予防における “ビタミン” の大切な役割とは?
2024年05月20日 | ブログ
若々しさの秘訣に4種類のビタミン いつまでも若々しい肌でいたいという人々の想いに応えて、世の中にはまるで“時間を戻す”ことを叶えてくれるかのようなスキンケア製品がたくさんあります。...
【Web掲載】美的.com、Precious.jpでアクティブサプリが紹介されました
2024年05月2日 | メディア掲載
美的.com 友利 新先生の「インナーケアルーティン|夜は質のいい睡眠へ導くサプリメントで美肌を育む!」でアクティブサプリ ビタミンA+Dとアクティブサプリ ビタミンA+C+Eをご紹介いただきました。 記事はこちら>> ...
【雑誌掲載】婦人公論、美的、VOCEでアクティブサプリが紹介されました
2024年04月11日 | メディア掲載
婦人公論(3月号) P,93わたしを癒やす美容時間 春こそ肌ぐすみの原因を一掃しよう!のなかでアクティブサプリ ビタミンA+C+Eが紹介されました。 美的(4月号)...
【Web掲載】otona MUSE webでアクティブサプリが紹介されました
2024年04月11日 | メディア掲載
otona MUSE web ...
1年間頑張った私へ、ビューティサプリを贈ろう!
2023年12月8日 | ブログ
2023年も残すところ約3週間となりました。いつもより少し贅沢をしたくなる、そんな季節ですね。今年は1年間頑張った自分へ、とっておきの“ビューティギフト”を贈ってみてはいかがでしょうか。今回は、美しい肌を目指して体の中からケアするために、お...
【Web掲載】kiitos.online、美的.com、CLASSY. onlineなどでアクティブサプリが紹介されました
2023年11月21日 | メディア掲載
kiitos.online 「サプリメントってどう選んだらいいの?サプリメント基本のQ&A|A Guide to Supplements②」の中で、ジャーナリスト 後藤典子さんにアクティブサプリ...
【雑誌掲載】otonaMUSEでアクティブサプリが紹介されました
2023年11月16日 | メディア掲載
otonaMUSE 12月号 「30代から知っておきたいオトナミューズ的更年期講座」の中で、アクティブサプリ ビタミンA+Dが掲載されました。 アクティブサプリの選び方に困ったら、 こちらのブログをチェック...
【ビタミンD】実は98%の人が不足!美容におすすめの栄養素
2023年10月27日 | ブログ
「ビタミンD」と聞くと何をイメージするでしょうか。もしかしたら、「骨を作るビタミン」という方が多いかもしれません。しかし、実は海外ではビタミンDは、肌や体など全身に大きな影響を与える栄養素として認知されています。近年の研究では、ビタミンDの...
製品一覧